竹中千春さん『ガンディー 平和を紡ぐ人』
- 岩波新書編集部

- 2018年2月2日
- 読了時間: 12分
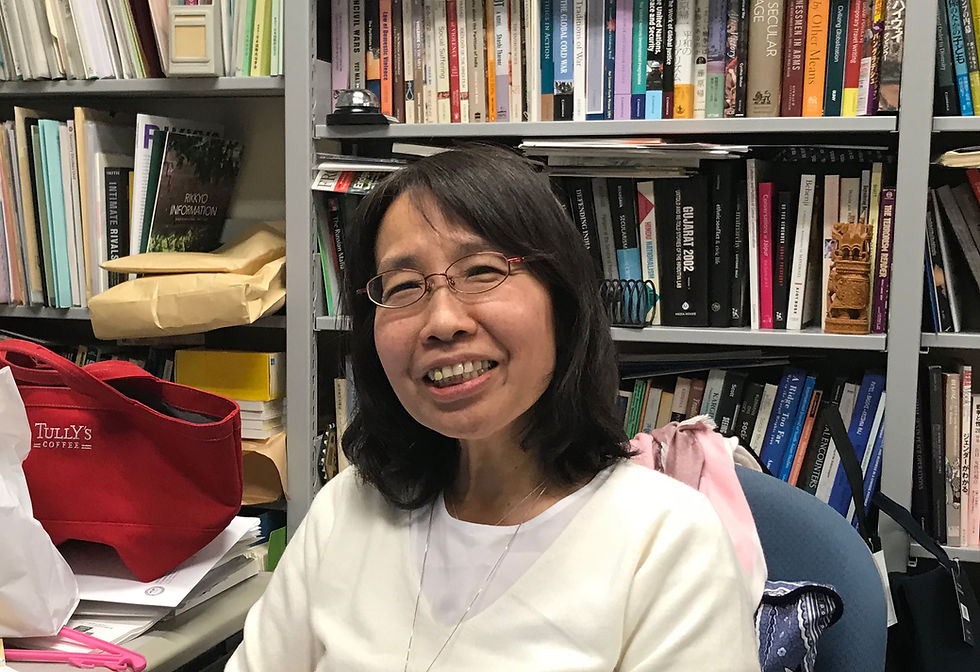
今年、2018年の1月30日は、ガンディーが暗殺されて70年でした。『ガンディー 平和を紡ぐ人』の著者、竹中千春さん(立教大学教授)にお話をうかがってきました。
* * *
──なんとか発売日に間に合いましたね!最後は時間との勝負でしたけど、先生が必死になって書く様子を見ていて、なんだかガンディーが書かせてくれているように見えました。無事書き終えて、何を感じていらっしゃいますか?
本当にありがとうございます。ガンディーもそうですが、彼と一緒に「歴史をつくった人々」が、この本を書かせてくれたのではないかと感謝の思いでいっぱいです。
ガンディーの本は、これまで何度も書こうとしたのですが、そのたびに挫折してきました。「はじめに」でも書きましたが、独立インドの初代首相になったジャワーハルラール・ネルーは、「ガンディーの伝記を執筆することは凡人には不可能だ」と言っています。振り返ってみると、ガンディーの伝記を新書で書くのは、まるでヒマラヤ山脈の頂を目指すような、無謀な試みだったと痛感します。でも、何とかできてよかったです。
──今年の1月30日はガンディーが暗殺されて70年でしたからね。
ええ、だからこそ、どうしても出さなければという思いが強かったです。世界にはいま、暴力の強い風が吹いているように見えます。1930年代との類似性を指摘する議論が、現実味を帯びて響いてくるほどです。こういう時代には、平和を説く人が危険に晒されやすくなります。ですから、非暴力と平和の思想を世界に示したガンディーの人生をいま語らずに、いつ語るんだという思いがありました。
研究を続けていると、歴史を創造した人々は、時間や空間を超えて、後から来る者たちに新しい歴史をつくるための知恵と勇気を発信し続けているのではないか、という感じがすることがあります。私が、ガンディーや彼とともに働いた人々からのメッセージを読者の方々に渡す役割を不十分にでも果たすことができたなら、本当に嬉しいです。
──でも、ガンディーというと、小学生のときに読んだ偉人伝を思い出してしまいます。私も最初のうちはそうでした。つい知っているつもりになっていて……。
たしかに、「ああ、あれね」という、いつか聞いたような「偉人伝」を連想してしまうかもしれませんね。偉大な人は偉大だ、みたいなお話は、そもそもストーリーとして退屈だし、お説教調なところが嫌ですよね。しっかり見習って勉強しなさい、というような。
じつは、世の中には、ため息をつくほど、膨大な数の「ガンディー伝」があります。インドではもちろんそうです。独立後のインドが、新国家の正統性を示し、そのために闘った人々を讃えるのに「国民の歴史」を書くことを奨励したから、というのが1つの理由です。その結果、古代の理想の王子ラーマの生涯を綴った叙事詩『ラーマーヤナ』のように、独立に身を捧げた「国民の父」ガンディーを主人公とする物語、つまり『ガンディーヤナ』が次々と編まれることになりました。まさに「正しい歴史」、学校でも学ばなければならない「正しいインド史」の一部なのです。
さらに言うと、ガンディーはインドの人々だけのものではありません。非暴力と平和の思想と運動の指導者として、世界中で尊敬を集めてきました。そこで、非暴力や平和を追求する人々もまた、ガンディーと彼の歩みに学ぼうと、たくさんの本が出版しています。こうした作品では、もちろん善意からなのですが、「正しい人」ガンディーを伝えたい、ガンディーの「正しい教え」を学ばせたいというトーンが、やや強く押し出されがちです。
そういうこともあって、今回の私の本では、なるべく偉人伝風の「ガンディー伝」ではないものを書こうと目指しました。要するに、書き割りの筋書きではない、ちょっとおもしろい偉人伝にしようとしたわけです。どこまで成功したかはわかりませんが。
──では、どんなふうにガンディーを描いたのですか?
そうですね、偉業を成し遂げた「マハートマ」としての側面よりも、激動の時代を懸命に生きた生身の「人間ガンディー」の側面を強調しました。しかも、年齢を重ねてどんどん変身する「人間ガンディー」を描こうと思いました。そもそも彼は最初から「マハートマ」ではなかったんですよ。仏教では人生を「四住期」といって、学生期・家住期・林住期・遊行期に分けます。この考え方にならって、ガンディーの人生を「4つの季節」に分けて捉えようという思考実験もしてみました。
ガンディーが生まれたのは1869年10月です。日本でいえば、ちょうど明治維新のころですね。比較的裕福な家に生まれましたから、子どもの頃の写真もちゃんと残っています。当たり前ですが、写真を見れば、彼が最初から「マハートマ」であったわけではないとわかります。ところが、じつは、けっこうこれは重要な発見なんです。
──たしかに私も意外でした。南アフリカ時代のガンディーの写真はとくにそうですね。「え?これがガンディー?」と思いました。スーツ姿がまたキマってるんですよね(笑)
はい、ガンディーはすごくおしゃれな人で、イギリス時代には髪型を決めるのに長い時間鏡の前で髪を梳かしていたそうです。面白いのは、写真の中のガンディーは、ファッションが変わるとともに、生き方のスタイルも、考え方の発展や新しい仕事の内容とともに変わっていくことです。伝統衣装を着た子ども、まるで西洋紳士の法律家、白い手紡ぎ手織りの布をまとった人というように、「人生の季節」の移り変わりとともに、生き方のスタイルがそのまま現れ出ている気がしますね。
だいたい「国民の父」なんて言われている人が、10代終わりから40代半ばまで、ほとんど外国で暮らしていたこと自体、あらためて考えてみると不思議です。それに、その間ずっと英国製のスーツを着て、革靴を履いて、英語で仕事をしていたんですよ。要するに、ガンディーの人生を見ただけでも、インド・ナショナリズムは純粋土着のMade in Indiaとは言い切れないのかな、ということがわかります。

南アフリカで弁護士事務所を開業していた頃のガンディー
──写真といえば、私は本の中でなぜか印象に残っている写真がありまして。有名な「塩の行進」で出発に備えて整列している人たちの写真ですね。何の変哲もない集合写真ですけど、何かすごく気高い雰囲気を感じるんですよね。誇りに満ちているというか。
ガンディーとともに「塩の行進」に出発した人々、「サッティヤーグラヒー」たちの写真ですね。たしかに、あの人々の姿には、私も心から人間的な感動を受けます。社会科学的に歴史を見ようとすると、およそ人間の行動について、経済的利益が大事だったからだろうとか、政治的権力を獲得するためだろうといった分析をしがちです。もちろん、そういう冷めた視点は大事ですが、人が何かをする動機はそれだけではない。「塩の行進」に向けて選抜された非暴力の戦士たちの写真には、ガンディーとともに命がけの行脚に出かける人々の、一人一人の勇気と決断が捉えられています。まさに、正義を実現しようとする人々の顔です。同じ人間として尊敬と感動を覚える、まさに「真実の瞬間」を捕まえた写真ですね。
──本のタイトルをどうするか、悩んでいらっしゃいましたね。一度は『ガンディー 平和を紡ぐ聖者』で決めましたけど、最後の最後になって副題を「平和を紡ぐ人」に変えました。どのようなお考えがあったのですか?
副題はかなり悩みました。ガンディーらしく、インドらしいものは何だろう、と。悩んでいるうちに、糸を紡ぐ彼の姿がぱっと思い浮かびました。糸を紡ぐように平和をつくる人。静かで温かく、親しみやすい師(グル)。頑固で怒りっぽいけれどチャーミングな、いつも人々と一緒にいるお父さん、おじいさんみたいな人。世間では「聖者」だと言われているけれど、じつは私たち自身のような近しい存在。本の帯には、そういう感じにマッチした、笑顔で明るいガンディーの写真を載せていただきました。「さあ、いらっしゃい、いらっしゃい、ガンディーの劇が始まりますよ」という感じですね(笑)
──たしかに、ガンディーといえば糸車を連想しますね。でも、よく考えたら、なぜ糸車なのか、知っているようで全然知りませんでした(笑)。今回の先生の本を担当して、その意味が初めてわかりました。なるほど、そうだったのか、と。
糸を紡ぐことは、静かで粘り強い作業ですが、誰もができる営みでもあります。女性でも、子どもでも、お年寄りでもできる。学校を出ていようが出ていまいが、裕福だろうが貧乏だろうが、都会の弁護士だろうが田舎の農民だろうが、関係ありません。ヒンドゥー、イスラーム、クリスチャン、シーク、仏教、ゾロアスターなど、信仰が異なってもよい。実際には、自分の体や手や指を使って働いている人々、つまり貧しい人々や家の中で作業している女性たちのほうが、お金持ちやエリートや指導者である男性たちよりも、上手にこなせる仕事です。
ふつう、「独立運動」「民族解放闘争」などと聞くと、勇ましくて男らしい、武器を持って敵を恐れず闘う、戦士や勇者のイメージが浮かびますね。でも、ガンディーは全然違います。彼は、まるで女性のように、貧しい農民のように、糸を紡ぎ、自らが身にまとう布を自分でつくることこそが解放であり、「それこそ、スワラージ(自治)だ」と呼びかけました。ものすごい逆説です。死を賭して行進したり、武器を取って闘ったりすることよりも、糸を紡ぐことのほうが重要だと宣言したのです。
──大衆運動を組織するなら、男性だけでなく、女性や年老いた人たちも参加できなくてはなりませんものね。
ええ、だからこそ、手紡ぎ糸の運動は急速に広まり、全インドのものとなりました。さらに、非暴力的で民衆的な戦い方は、国境や民族や宗教や時代を超え、世界中に影響を与えました。ここにガンディーの「創造」というか、「発明」があると思います。まさに、キング牧師やスティーブ・ジョブズ、その他の多くの人々が尊敬し、学び、見習おうとしたアイデア、人間的なレベルに留まらない、社会的なレベルでのクリエーション、イノベーションですね。ガンディーはビジネスマンではないですから、アイデアの特許など取りませんでしたし、教祖ではないので「ガンディー教」も唱えたりしなかったのですが(笑)
そのガンディーの「創造」を支えたのが、ガンディーとともに「歴史をつくった人々」でした。これまで書かれてきた「歴史」というものは、どれも国家や支配者を主人公にしたものでした。どの国ができたとか、誰が政権を取ったとか。言いかえれば、「国家の歴史」「支配者の歴史」です。ガンディーがインドを独立させたという偉人伝もまた、そういう「歴史」のうちのひとつです。しかし、本当にそうなのだろうか。膨大な数の人々がガンディーを信じ、彼と行動をともにしたからこそ、ガンディーの「奇跡」が起こったのではなかったか。私はそう考えるのです。
──"ダルシャン"というインドの風習でしたか、「マハートマが来たぞ!」と言って、手を合わせながら駆け寄る民衆たちですよね。
ええ、そう考えると、じつはガンディーに単純に付き従ったと思われてきた「人々」こそが、歴史の主人公だったのではないか、という議論も可能になります。ここでもまた発想の転換ですね。こういう発想が歴史研究に持ち込まれるのは、それまで力を持たなかった人々がエンパワーするとき、つまり人々の力で独立や自治が実現したり、民主化が進むときなのです。
1970年代に独裁的だと批判されたインディラ・ガンディー政権が"ジャナタ(people)"を掲げる勢力に選挙で敗北した時代以降、歴史研究の民主化というか、民衆の登場する歴史叙述を求める運動が始まりました。たとえば、かつてムッソリーニに投獄されたイタリアのマルクス主義者アントニオ・グラムシが「下層階級の人々」を指して使った"サバルタン"という概念を掲げた、サバルタン研究がその一例です。こうした社会史や民衆史の試みについては前に、『サバルタンの歴史―─インド史の脱構築』(ラナジット・グハほか著、岩波書店)という本を翻訳してご紹介したことがあります。
サバルタンの視点から歴史を見ると、それまでは歴史の表舞台に登場させてもらえなかった「名も無き人々」の顔や姿がクローズアップされてきます。かき消されていた、人々の声なき声も聴こえてきます。身近なしがらみに縛られ、日々の出来事に振り回され、いろいろなことを心配し恐れながら生きている、私たちのようなごく普通の人々ですね。こういう人々が勇気をもって立ち上がり、知恵を絞って考え、自分たちの問題を解決するためにはガンディーの指導に従おうと決意したから、「塩の行進」が可能となったのではないか。そういう解釈になります。
「聖者」や「マハートマ」だけが歴史をつくったのではない。私たちよりももっと苦しい立場にあった人々も含めて、多くの人々が歴史をつくった。もっといえば、インドの膨大な民衆たちが「マハートマ」を選び、創造したのだ、と。私は幸いにも、サバルタン研究をはじめ、「人々」に光を当てようとするさまざまな研究や議論から、このような視点を学ばせてもらいました。

「マハートマが来たぞ!」。ダルシャンを求めて、車中のガンディーに駆け寄る民衆たち
──では、最後に読者の方にメッセージをお願いします。
ガンディーの晩年は、ナチズム、ファシズム、軍国主義が台頭する時代でした。国家や武装集団だけでなく、民族や神を持ち出す勢力も、階級闘争を押し出す勢力もみな、暴力で相手を打ち負かし、倒そうとする時代でした。そういう時代のなかで、ガンディーの非暴力と平和の思想は、無抵抗で敵に屈服する敗北主義的なものだと、非難する声も高まりました。
そんなとき、一人のジャーナリストがガンディーにこう尋ねたのです。「世界の人々へ、ひと言メッセージをくださいますか」。ガンディーは即座にこう答えました。
My life is my message.
今回の新書の帯に載せてもらった言葉ですね。大変に重い言葉です。いろいろな受け止め方があると思いますが、私には、ガンディーはこう言っているような気がします。「私の人生にも、過りや失敗がなかったわけではありません。けれども、自分なりに、精一杯、頑張って生きてきました。為すべきこと一つ一つを決断し、それを実行するべく、最大限の努力を払ってきたつもりです。真理(サッティヤー)を求めて真摯に祈り、ダルマ(義務)を達成しようと、神に導かれながら、いつも真剣に戦ってきたのです。ぜひ、その歩みを見てください」と。
ガンディーの真理を求める戦いは、正義や善が圧勝し、不正や悪を力で倒すという二項対立的なものではありませんでした。自分の中にも悪があるし、相手の中にも善がある。ここが重要な点ですが、平和への非暴力的なステップは、そのような矛盾をはらんだ人間的な存在そのものを受け入れ、自分と他者双方への尊敬と愛情と許しを抱くところから生み出されるのではないでしょうか。
ガンディーに関心を持たれる方は、非暴力だけでなく、平和にも深い関心を寄せている方が多いのではないかと思います。21世紀の今、世界はこれまでになく、暴力の風がとても強く吹いています。日本に暮らす私たちも、そのような風の中で生きています。ガンディーなら、今、何を考えるでしょうか? 何をするでしょうか? 歴史を学ぶということ、そして歴史の中で大きな仕事をした人の生き方を学ぶということは、その人の思考の方法を学ぶことではないかと思っています。この本が、皆様とガンディーとの対話のきっかけになれば、本当に嬉しいです。
──ありがとうございました。
2018年1月16日、立教大学にて
聞き手:編集部 永沼浩一




コメント