『ユーゴスラヴィア現代史 新版』によせて
- 岩波新書編集部

- 2021年8月30日
- 読了時間: 11分
更新日:2021年9月2日
山崎信一・鈴木健太
※8月27日に刊行となった『ユーゴスラヴィア現代史 新版』。歴史学の名著として知られた旧版を改訂するさなかに、著者・柴宜弘さんが急逝されました。その思いを引き継いで出版作業にあたられた山崎信一さん、鈴木健太さんに、本書の意義をご執筆いただきました。
柴宜弘著『ユーゴスラヴィア現代史 新版』が、このたび無事に刊行の運びとなった。本来であれば、著者自身がその紹介にあたるところであろうが、著者の柴先生は、残念ながら本年5月28日に急逝された。1996年に岩波新書の一冊として、『ユーゴスラヴィア現代史』(以下、「初版」)が出版されてから25年を経て、今回「新版」の刊行に至った詳しい経緯、かつてのゼミ生が校正を引き継いだ経緯などは、「新版」巻末の追記に記されているので、詳しくはそちらをご覧頂ければと思う。ここでは、紙幅の関係もあり追記において触れることのできなかった点、すなわち本書がユーゴスラヴィア研究において持つ意味、そして柴先生自身がこれまで長きにわたり進めてきた研究の成果がどのようにこの「新版」に反映されているのかといった点を中心に考えてみたい。本書の校正作業に携わるなかで、「初版」と「新版」の内容に細かく目を通したが、非常に多くの発見があった。そして本書の各部分における先生の記述の動機にも少し迫ることができたのではないかと思う。
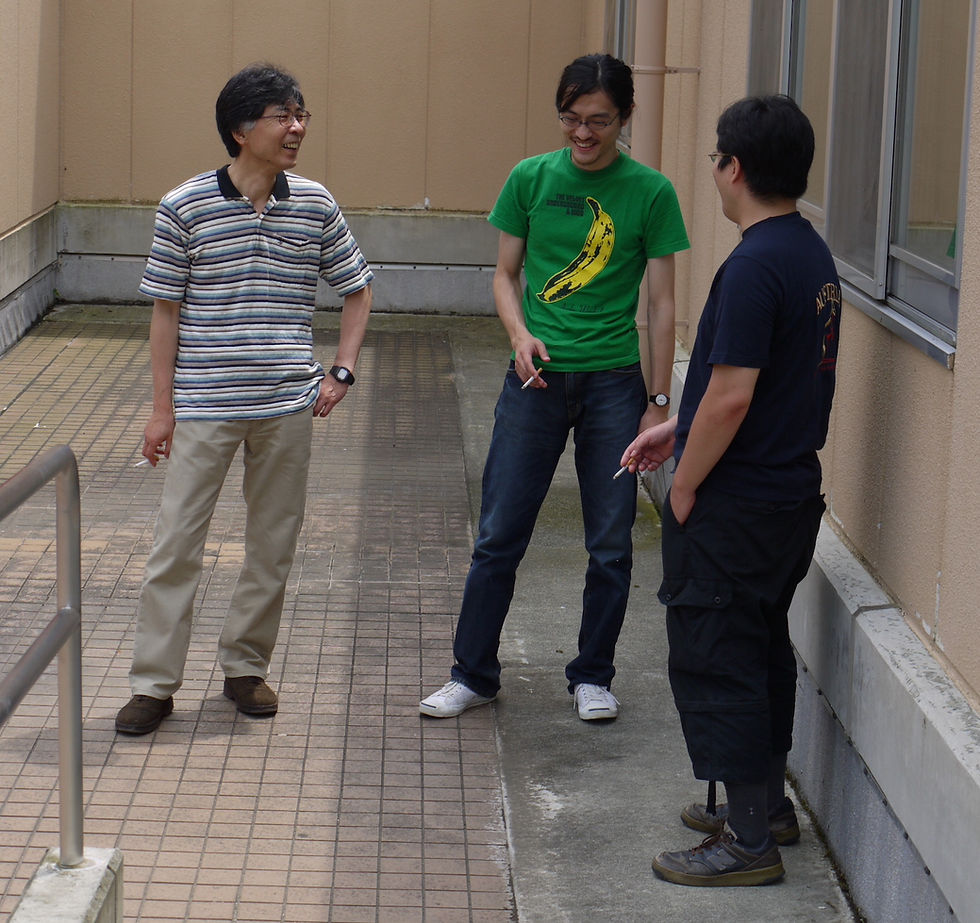
柴先生(左)と筆者。2009年の合宿にて。
* * *
柴先生は、1946年に東京の下町の職人の家庭に生まれた。かつて先生が語った、組織に頼らずコツコツと全工程をひとりで成し遂げる職人の父の姿は、先生自身の研究姿勢とも重なって見える。その後、先生の研究人生にとって大きな意味を持ったのは、1970年代半ばに、当時のユーゴスラヴィアのベオグラード大学に政府給費留学生として留学したことであろう。ユーゴスラヴィアへの留学は、この地域の歴史を研究する原点となったのみならず、この地域に多くの知己を得て、その後終生変わることのない交流の基盤を作ったという点でも大きな意味があったと思われる。先生がユーゴスラヴィアに関心を持った大きな理由の一つは、自主管理社会主義と呼ばれていた独自の社会主義体制だったと聞いているが、その後はそこに留まらずに幅広く研究を進めていった。1980年代における先生の関心は、ユーゴスラヴィアにおける近代史をめぐる歴史論争や「青年ボスニア」といったテーマ、さらにはマケドニア問題、ボスニア・ムスリムの問題、アルバニア人問題など、ユーゴスラヴィアの連邦制と民族問題に関わるテーマにも広がっている。一方で、その草創期から東欧史研究会の活動にも積極的に関わり、狭いユーゴスラヴィア研究に留まらない東欧史、あるいはバルカン史への関心も持ち続けていた。(先生の個々の研究についてより詳しくは、以下を参照。https://ci.nii.ac.jp/nrid/1000050187390)
1990年代のユーゴスラヴィア解体と内戦は、柴先生の研究歴にとっても大きな転機となるできごとだった。数少ない専門家としてメディアへの登場の機会も増え、多忙な日々を過ごすことになった。ユーゴスラヴィア紛争は、「情報戦争」でもあり、多くの一面的で偏った見方、事実に基づかない見解が広がっていた。先生自身は、必ずしも積極的にメディアに出ることを望んだわけではなかったと思うが、専門家として、そうした偏りを排することがその動機となったのだろう。本書の「初版」執筆の動機もその点が大きかったと思われる。
1990年代以降の先生の研究も多岐にわたるものだったが、その中でも大きな柱となっていたものの一つはバルカン地域研究の確立であった。歴史学の枠にとどまらない学際的な分野を確立することで、国民国家を相対化する視点を提供する意義を持つものであった。そしてもう一つの柱が、本書にも取り上げられている歴史教育の問題である。紛争が終わり当事者間の和解が課題となるなかで、歴史教育の分析と国民史教育の相対化の必要が強く認識されるようになり、先生はいち早くそれに取り組んだ。そしてその関心は、歴史教育の前提となる、各民族のナショナル・ヒストリーの問題にも及んでいる。また、幅広い人脈を生かし、2000年代には複数回にわたりこの二つのテーマを扱う国際会議を主催している。2004年には、ヨーロッパ現代史の大家マーク・マゾワーを自ら組織した東京大学での国際シンポジウムに招請している。こうした研究歴を振り返ると、本書には先生の研究の集大成としての意味があることも見えてくる。
* * *
本書の特徴や意義を位置付けるとすれば、以下の三つの点から論じることができるだろう。第一に、本書は、ユーゴスラヴィアの歴史を知るための入門書であり基本文献となりうるものである。日本語で読むことのできるユーゴスラヴィアの通史としては、解体前に書かれ、先生自身も翻訳に関わった翻訳書(スティーヴン・クリソルド編、田中一生・柴宜弘・高田敏明共訳『ユーゴスラヴィア史』恒文社、1980年、増補第2版1995年)を別にすれば、本書がほぼ唯一のものである(また、クリソルドの訳書は1960年代で叙述が終わっている)。加えて本書では、第1章で扱われるユーゴスラヴィアの建国に至るまでの各地域の歴史、そしてこの「新版」ではユーゴスラヴィア解体後の30年間の各地域の歴史が、コンパクトながらもそれぞれを有機的に結び付けて叙述されている。今後とも長きにわたり、ユーゴスラヴィア史を考える際に最初に参照される文献であり続けるのではないかと思う。
第二に、新書という形をとりながらも、本書はユーゴスラヴィアの近現代史を包括的に検討した専門書としての特質を持っていると言えるだろう。「初版」に関しても、この「新版」に関しても、先生自身、自らの研究の集大成のひとつであると考えていた。実際に本書を注意深く読んでみると、そのことに気付かされる。とりわけ先生のライフワークとも言える歴史教育と歴史叙述の問題に関しては、本書の各部分に研究の成果が反映されている。また、そもそもユーゴスラヴィア史の位置付けをめぐる問題についても、本書は明確な立場を打ち出している。解体を経験した後、ユーゴスラヴィアの歴史をどう位置付けるのかに関しては、実際にさまざまな見解がみられた。旧ユーゴスラヴィア圏においては、社会主義期に広く見られたいわゆる「パルチザン神話」が解体され、現代史叙述の共通の基盤が失われ、ユーゴスラヴィアの歴史を再解釈する動きも進んだ。それは主としてセルビア、クロアチア、スロヴェニアなどの各民族のナショナル・ヒストリーの立場からの解釈であった。言い換えればそれは、各民族の利害から見て、ユーゴスラヴィアという統一国家がどう理解されるかということであった。ゆえに、ユーゴスラヴィア史の位置付けは、民族ごとに極めて大きく乖離するものとなったのである。一方、欧米における研究にとって大きなテーマとなったのは、1990年代の連邦国家解体と紛争であり、その要因を探る試みとしてユーゴスラヴィア史が編まれる傾向がしばしば見られた。欧米言語による通史の多くは、紛争直後の2000年代前半までに刊行されている。比較的最近になって出版されたものを含め、それらの著作では、ユーゴスラヴィア史の記述を1990年代の解体と紛争で一区切りとするものが主流で、21世紀を含む解体後の時代を取り上げたものは少ない。
これに対して本書は、終章の冒頭においてドラゴヴィチ=ソーソの議論を発展させつつ論じることで、解体要因への関心に応えている。そしてそれに留まらず、ユーゴスラヴィアの継承諸国の解体後30年の歴史を有機的に再構成し、解体後のこれらの国々の歴史もまた、ユーゴスラヴィアの試みの延長の上に捉えられると位置付けており、この点が本書の大きな特徴となっている。「初版」において重要な論点となった「実験国」としてのユーゴスラヴィアの特質は、解体を経ても「小ユーゴ」となったボスニアの現状に引き継がれており、また継承諸国の相互の関係もユーゴスラヴィアの経験を色濃く反映したものであり、そこではユーゴスラヴィア史はユーゴスラヴィアの解体後も視野に入れて論じるべきものであるという主張がしっかりと裏付けられている。本書終章を締めくくる一文「ユーゴスラヴィアの現代史はまだ幕を下ろしていない。」は、その意味でも非常に示唆的である。
第三に、本書は、ユーゴスラヴィアに惹かれ、その歩みに寄り添い続けた歴史家の同時代史としても読むことができるだろう。本書の第5章以降が扱うのは、柴先生が同時代に体験した時代でもある。「はじめに」で紹介されている複数のパスポートを持つ女性のエピソード、あるいは第6章冒頭のボスニア出身の歌手ヤドランカの話題など、個人的な体験を下敷きにした記述からもそうした点がうかがえる。留学以来、ユーゴスラヴィアに関わってきた先生にとって、その解体と紛争はとりわけ残念なできごとであっただろうと思う。ユーゴスラヴィアへのある種の思い入れが、分析の眼を曇らせるようなことは先生には一切なかったが、それでも、かつて一つの国に暮らした人々が、少なくとも相互の対立ではなく共存や多様性を尊重する方向に向かうことは強く願っていたと思う。この点は、「新版」での加筆部分において、対立の側面だけではなく、地域協力や過去の克服に関して丹念に拾い上げていることからも見てとれる。

* * *
本書の「初版」の刊行から今回の「新版」までの間には25年の間隔がある。「初版」の執筆の動機として大きかったのは、ユーゴスラヴィア紛争が激化するなかでさまざまに生じた玉石混交の見解に対し、結論ありきではない形でユーゴスラヴィアを歴史的に位置付けることであった。今回の「新版」は、そうした「初版」の動機は維持しながらも、紛争から時間が経ち少し落ち着きを取り戻した継承諸国の動きを追いながら、改めてユーゴスラヴィアの歴史を、ヨーロッパ史や世界史というより大きな文脈で論じることにも重きを置いている。
「新版」で新たに加筆されたのは、第6章の後半と第7章で、終章に関しては全面的に改稿されている。また、それ以外の「初版」から引き継がれた部分にも、必要に応じて細かい訂正や加筆がなされている。この部分で、唯一、項の単位で加筆がなされているのは、第2章3節の項「パリ講和会議と新生国家の国際的承認」である。第一次世界大戦100周年を契機に2010年代半ばにさまざまな共同研究がなされたが、柴先生も加わった共同研究の成果がこの部分に反映されている。第6章の後半と第7章の新稿部分においては、継承諸国それぞれの動向、地域協力の進展と欧州統合、過去の見直しといった点を有機的に描き出している。終章に関してのみ、「初版」からの全面的な改稿がなされているが、その本質的な方向性は一致するものだろう。例えば、「初版」の終章では、「ユーゴ内戦と日本」の項において、ユーゴスラヴィアの問題をどうわれわれ自身の問題として捉えるべきかを問うている。「新版」においてもそうした問題意識は一貫しており、「ユーゴ内戦と暴力」の項においては、ユーゴスラヴィア紛争に伴う暴力が決してこの地域に特殊なものではなく、むしろ近現代史一般に共通する普遍的な現象なのであり、日本の歴史にも当然内在するものだと鋭く指摘している。
柴先生は、「はじめに」において、文化の問題を包括的に取り上げなかった旨述べているが、本書には各所にユーゴスラヴィアの映画が取り上げられており、それを補っている。本書の中でも感じられるように先生は映画好きでもあり、10年以上にわたり旧ユーゴスラヴィア映画の上映会の組織にも携わっていた。「新版」で加筆した部分で紹介されている映画はあまりないが、補足として先生がパンフレットへの解説執筆などで関わった映画を3本挙げておきたい。いずれもボスニア紛争を題材としたもので、タノヴィッチ監督『ノー・マンズ・ランド』(2002年、2007年に舞台化)、ジュバニッチ監督『サラエボの花』(2006年)、同監督『アイダよ、何処へ?』(2021年)である。
本書の巻末には主要参考文献が一覧になっている。「初版」において41冊挙げられていた邦語書籍は、「初版」刊行後のものを中心に「新版」においては58冊に増えている。これを見ても、関連する諸分野における研究の進展は著しい。しかし研究の専門化が進むことは、一方で一種の研究の蛸壺化を招くものでもあり得る。本書は研究が専門化するなかで、ユーゴスラヴィア史とは何かを考える際に立ち返るべき一つの参照軸としても意味があるだろう。そして私たちも、柴先生の薫陶を受けたユーゴスラヴィア研究者として、この先さらに長い年月が経過した際、果たして「ユーゴスラヴィアの現代史」が終わりを迎える日が来るのかを見届けたいと思っている。
山崎信一(やまざき・しんいち)
1971年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科単位取得退学。現在、東京大学教養学部非常勤講師。専門はユーゴスラヴィア地域の近現代史。主な著作に、『アイラブユーゴ』1–3(社会評論社、共著)、『ボスニア・ヘルツェゴヴィナを知るための60章』(明石書店、共編著)など。
鈴木健太(すずき・けんた)
1980年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科単位取得退学。博士(学術)。現在、神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部講師。専門はユーゴスラヴィア地域の現代史、地域研究。主な著作に、『アイラブユーゴ』1–3(社会評論社、共著)、「ユーゴスラヴィアにおける1989年」(『思想』2019年9月号)など。




コメント